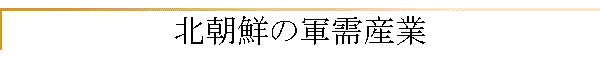
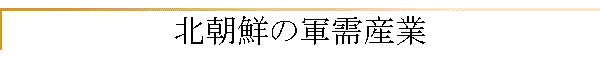
ソ・チュソク/韓国国防研究院責任研究委員
![]()
社会主義の経済体制は、国家が中心となる中央集権的計画経済を特徴とする。従って、個人と企業、国家が有機的な関係を結び、生産活動に任じる資本主義経済体制より経済活動での国家の要素は絶対的で、その過程において国家が1次的に必要とする活動に対して、政策的関心が優先的に付与される。国防部門は、正にこのような国家の1次的関心領域と言えるが、この点において多くの社会主義国家は、軍需部門を重視してきた。
社会主義国家が軍需部門に多くの投資を行うもう1つの背景には、やはり彼らの世界観も重要に作用している。資本主義国家との対決を通して、体制生存も成し遂げ、世界共産化も達成するという社会主義理論に従い、社会主義国家は、これを準備するための軍事力を重視した。社会主義の世界観と体制内部のメカニズムによる軍事力重視、軍需部門重視は、直ちにこの部門に対する過度な投資を生み、経済的生産誘発効果が相対的に小さいこの分野が重視され、直ちに経済体制全般の非効率と生産沈滞を呼び起こした。これは、곧
社会主義圏崩壊の一要因として作用した。
![]()
■北朝鮮の「先軍政治」の経済的意味
北朝鮮は、1990年代後半から金正日国防委員長の軍部優先、軍重視政策を「先軍政治」と命名し、このような特有の政治方式で体制を
導いていくことを明らかにしている。1997年7月に「先軍後労」という用語で初めて登場したこの概念は、当初、金日成前主席死後の危機管理体制の速成と見られたが、今は、より長期的な金正日式統治方式として理解されている。
概念上、先軍政治は、「軍隊を重視し、軍隊を強化するのに、先次的力を注ぐ政治方式」で、基本的に政治的次元の意味として理解されている。北朝鮮での先軍政治は、軍の役割拡大及び軍部優待、軍事
主義国政運営(軍風)方針として要約されるが、金正日体制においてこれを見せている多様な兆候が現れている。ここには、先軍革命領導及び先軍政治に対する直接的強調、軍関連機関の地位上昇及び権限拡大、軍部核心人士の序列上昇、金正日委員長の軍人士優待及び軍関連活動増大、軍民一致運動のような社会の軍風重視等が含まれる。
最近にも、北朝鮮では、先軍政治に対する強調がほとんど減っていない。上で言及したように、一旦経済回生と体制維持のための攻勢的接近として、強盛大国建設が強調
されても、度が過ぎた対外開放や改革を警戒し、部分的な経済政策的調整が行われている状況と連携され、むしろ社会統制の規制として、先軍政治は、更に意味が広がるものと理解される。今は、先軍政治が強盛大国建設の「核心的方法論」にまで規定されている。
金正日委員長体制の核心的スローガンとして、先軍政治が実際の軍事力や経済部門にいかなる影響を与えるのかに対しては、相反した分析がある。先ず、先軍政治が概念上軍隊強化に総力を傾けることだが、実際にどの程度北朝鮮の軍事力強化と連結するのかに対して、考えてみる必要がある。北朝鮮の文献では、先軍政治を通した軍事力強化が言及されており、この点においてその軍事的意味を無視することはできない。例えば、2 0 0
1年4月、最高人民会議報告では、「内閣は、党の先軍革命路線を生命線とし、国の軍力を百方に強化するのに、続けて大きな力を入れます。全社会に銃隊重視、軍事重視気風を
確固として立て、軍事先行の原則を徹底して堅持することによって、人民軍隊の戦闘力を強化するのに、国の経済的潜在力を最大限に組織動員しなければならない」
と語ることによって、経済力の積極的な軍事的活用を言及している。
しかしながら、その結果が実際の軍事力強化に繋がると解釈するのは、困難な部分もある。先軍政治に従い、軍が優先視され、経済力の軍事投入が強調
されるとしても、果たして経済的疲弊が確然な状況において、軍事力強化面においてどの程度成果を収めるのかは疑わしい。むしろ、北朝鮮軍が体制維持のため、役割を拡大する過程において、政治・経済的領域拡張に従い、国境線守備と平壌統制等の業務を担当し、相当数の兵力が経済建設及び工場・農場警備、道路・発電所等のインフラ建設等に派遣されることによって、むしろ軍事力自体には、否定的な影響を
与えるものと理解され得る素地がある。実際に先軍政治が主唱された1990年代後半以降、北朝鮮の軍事力は、大きく変化しておらず、ただミサイル開発、長射程火砲の前方配置拡大等、一部措置だけが断行された。次の<表1>
で見るように、兵力の増強とこれに従った部隊数の増加以外に大きく増強された部分がないものと判断される。
<表1>北朝鮮軍事力の変動(1995〜2000)
| 区分 | 1995 | 2000 | |||||
| 兵力 | 地上軍 | 91万余名 | 104万余名 | 100万余名 | 117万余名 | ||
| 海軍 | 4.6万余名 | 6万余名 | |||||
| 空軍 | 8.4万余名 | 11万余名 | |||||
| 主 要 戦 力 |
地上軍 | 部隊 | 軍団 | 19個 | 20個 | ||
| 師団 | 50個 | 67個 | |||||
| 旅団 | 99個 | 78個(砲兵30余個旅団除外) | |||||
| 装備 | 戦車 | 3,800余台 | 3,800余台 | ||||
| 装甲車 | 2,600余台 | 2,300余台 | |||||
| 野砲 | 10,850余門 | 12,500余門 | |||||
| 海軍 | 水上戦闘艦 | 434隻 | 430余隻 | ||||
| 支援艦 | 330余隻 | 470余隻 | |||||
| 潜水艦(艇) | 26余隻 | 90余隻 | |||||
| 空軍 | 戦術機 | 850余機 | 870余機 | ||||
| 支援機 | 790余機 | 840余機 | |||||
資料:国防部(1995〜96/2000)、「国防白書」、大韓民国国防部
このように、先軍政治路線自体がその政治的意味に比べて、軍事力の劇的な強化として現れず、経済的にも軍需産業の回復及び成長を導き出せずにいる。むしろ、先軍政治は、 経済的にその弊害がより大きい。例えば、先軍政治が強調され、一線の現場において党や国家機関に対して軍部隊が声を高める場合が数多く、それに従い経済建設に軍が動員された場合には、目標が比較的 簡単に達成されるというが、これは、その位正常的な資源配分を軍が物理的に圧迫し、歪曲した結果として、むしろ経済全般の非効率を焚き付けるものと言える。
![]()
■北朝鮮の軍事経済
北朝鮮の軍事部門は、社会主義圏特有の体制的構造、対外対決的政策、先軍政治等により、過度に強調されている。北朝鮮の軍事経済(第2経済)は、民間経済(人民経済)と並列的に管理されており、国家資源が優先的に配分されている。
北朝鮮の軍事部門は、当座の人的な規模面において過度である。人民武力部が管理する北朝鮮の軍隊は、117万余名で、全人口の5%水準に該当する世界最高水準である。その外に、党機構である中央軍事委と秘書局軍事部、作戦部、軍需工業部、国家機構である国防委員会と第2経済委員会、軍需動員総局等が軍事部門に関与しており、国家保衛部、人民保安省等、各種軍関連機構があり、人民軍外管理人員だけでも数十万名を超えるものと推定されている。ここに予備兵力740万余名を合わせれば、簡単に全人口の40%ラインに達する。この膨大な人力が軍事部門に投入されている点において、その経済的意味、特に経済的非効率が
著しいだろう。
北朝鮮の軍事部門は、エネルギーと食糧の最大消費処の中の1つである。平時、北朝鮮軍の食糧消費は、全所要の5%を大きく上回り、石油類の消費は、その3倍近くとなる。また、北朝鮮軍は、戦時に備えて、100〜120日分の食料と油類を備蓄しているが、これは、該当部門生産量の30〜40%に該当し、エネルギー及び食糧難を加重させている。
一方、北朝鮮の予算において、軍事費が占める比重は、発表より最小3倍以上高いものと理解される。北朝鮮の発表軍事費は、最近、毎年13〜14億ドル程度であるものと出ているが、実際の軍事費は、
隠蔽部分、購買力の差異等を勘案すると、その3〜4倍に達する45〜50億ドルに達するものと評価される。特に、北朝鮮軍の軍事費は、軍事予算以外の他部門に散在され隠蔽されており、また、北朝鮮軍には、部隊別に「自力更生」の原則が適用され、例えば、1種(飲食物)の場合、主食のみ供給され、副食は、自主充当するようにされており、全体的な費用算出が
非常に困難な構造となっている。
<表2>北朝鮮の年度別軍事費規模(1991〜2000)
(単位:億ドル)
| 年度 | GNP (韓国銀行) |
総予算 (北朝鮮発表) |
軍事費 | GNP対比 軍事費比率(%) |
総予算対比 軍事費比率(%) |
交換率 (北朝鮮ウォン/米ドル) |
| 1991 | 229 | 171.7 | 51.3(20.8) | 22.4 | 29.9(12.1) | 2.15 |
| 1992 | 211 | 184.5 | 55.4(21.0) | 26.3 | 30(11.4) | 2.13 |
| 1993 | 205 | 187.2 | 56.2(21.5) | 27.2 | 30(11.4) | 2.15 |
| 1994 | 212 | 191.9 | 57.6(21.9) | 27.2 | 30(11.5) | 2.16 |
| 1995 | 223 | 208.2 | 63.0 | 27 | 30 | 2.05 |
| 1996 | 214 | ? | 57.8 | 27 | ? | 2.14 |
| 1997 | 177 | 91.0 | 47.8 | 27 | 52 | 2.16 |
| 1998 | 126 | 91.0 | 47.8(13.3) | 37.9 | 52(14.6) | 2.20 |
| 1999 | 158 | 92.3 | 47.8(13.5) | 30 | 51(14.6) | 2.17 |
| 2000 | 168 | 93.6 | 45-50(13.6) | 27-30 | 48-53(14.5) | 2.18 |
注:1995〜98年は暫定推定値、括弧内は北朝鮮公式発表値及びそれによる計算値である。
資料:大韓民国国防部(2000)、「国防白書2000」;韓国銀行(2001)、「2000年北韓GDP推定結果」から計算した。
![]()
■北朝鮮の軍需産業
北朝鮮の軍需産業政策は、社会主義体制の特性と1960年代初盤の「4大軍事路線」に立脚し、集中的に育成された。北朝鮮の軍需産業政策は、軍事装備自給自足体制の確立、軍需産業施設の地下化、人民軍隊の装備質的向上、軍需産業施設の戦略的配置、有事の際の戦時転換体制の確立、戦時予備用戦略部鬱しの平時備蓄確保等を特徴とする。
北朝鮮の軍需産業は、朝鮮戦争と1960年代の「経済建設と国防建設の併進策」に従い建設されてきた。朝鮮戦争以降、北朝鮮は、「経済より軍需工業を優先」する政策を推進し、軍需産業と関連がある機械、金属、化学工業等、基礎産業の発展に
重点を置いた。その後、1962年、労働党第4期4次全員会議において、4大軍事路線を公式採択した後、経済建設と国防建設の併進策を党の基本方針化し、急激な発展を
成し遂げている。1960年代後半以降には、国防での自衛を目標に自主資源と技術を基盤にした自立的軍需産業の育成に力を注いできた。
北朝鮮の軍需産業発達過程を時期別に見てみれば、次の通りである。1940〜50年代には、生産施設復旧及びロシアの武器体系を導入し始め、1960年代は、模倣生産を主とする小火器類生産及び軍需産業の基盤拡張の時期で、このときからAK小銃、重機関銃、迫撃砲、高射銃、放射砲、小型魚雷艇、高速警備艇等が生産された。1970年代は、北朝鮮の重火器及び主要戦闘装備を自主開発・生産し始めた時期で、このときから戦車、装甲車、170mm自走砲、潜水艇、高速艇等が生産された。1980年代には、新型武器生産、導入を含めて、量的拡張から質的改善への転換が指導され、在来式武器と火砲は100%、戦車及び装甲車は90%の自給率が確保され、新たに240mm放射砲、Mi-2ヘリ、Yak-18訓練機等が自主生産され始めた。また、1990年代には、核兵器及び長距離ミサイルの開発が推進され、Scud系列のミサイルとノドン1号、テポドン・ミサイル等が開発された。
![]()
■北朝鮮の軍需産業現況
北朝鮮の軍需産業体系は、党・政組織に機能別に分散されているが、全般的な業務は、党の直接的な統制下に進行されている。党機構としては、中央軍事委員会と党軍需工業部において基本政策を決定し、党第2経済委員会において実質的な政策を執行する。また、政府機構としては、国防委員会及び隷下の人民武力部、総参謀部等において、党軍需工業部と
協調し、生産された武器の検数及び配給を担当している。その外に、内閣は、国家計画委員会において年間軍需生産計画を最終作成し、党中央軍事委員会に上程し、経済関連内閣省傘下の工場及び企業所は、第2経済委員会傘下軍需工場の武器生産に必要なエネルギーと所要資材等を供給する。
現在、北朝鮮には、銃砲工場40余ヶ所、機甲車両工場10余ヶ所、艦艇造船所10余ヶ所、弾薬工場50余ヶ所等、計180余ヶ所の軍需工場があり、これは、GDP全体の1/4程度を生産しているものと知られている。北朝鮮の軍需工場は、大部分、慈江道、平安北道、咸鏡南道等、戦略的後方地域(山間内陸地域)に位置し、戦時に被害を最小化できるように地下化又は半地下化されている。北朝鮮は、軍需工場の位置と生産される武器の種類を
隠匿するために、軍需工場別に×号工場等の別称を付与しているものと知られている。
<図>北朝鮮軍の組織と軍需産業
資料:ソンチェキウェ(1999)、「北韓軍事体制研究」。韓国国防研究院報告書
![]()
■北朝鮮の対外軍事販売
北朝鮮の軍需産業は、対外経済関係において相当な位相を占めたが、脱冷戦以後、
漸次位相が下落している。武器輸入は、輸入額全体に対して、冷戦当時には、平均20〜30%水準だったが、経済難の下では10%以下に下落し、武器輸出もやはり冷戦当時の15〜20%水準から、1990年代中盤以降には、5%以下に下落した。
このような状況において、北朝鮮は、対外戦略武器輸出に対して、大きな関心を持ち始めた。北朝鮮のミサイル開発は、1980年代初めにエジプトからScud-Bミサイルを導入し、逆設計方法でこれを
元に戻すことによって始められたと知られているが、その後、積極的な対外販売が行われた。北朝鮮は、1987〜88年にイランに改良型Scud-Bミサイルを100余基輸出したのに引き続き、1990年代初めには、Scud-Cの量産体制を備え、毎年100〜150基をイラン、シリア、インド等の地に輸出したと知られている。また、北朝鮮は、テポドン1号ミサイルをエジプト、リビア、シリア等に技術又は部品輸出形態で販売しているものと知られており、テポドン系列ミサイルの開発過程において、イラン、パキスタン等と共同開発する方式を追求しているものと判断される。
勿論、現在も、北朝鮮の在来武器輸出も進行中だが、北朝鮮は、高射砲、放射砲、迫撃砲、AK小銃等をベトナム、タイ等、東南アジア諸国に販売し、潜水艇を
アラブ首長国連邦とベトナム等に多数輸出したものと知られている。特に、北朝鮮は、国際社会のミサイル輸出中断の圧迫により、1997年頃からミサイルの代わりに弾薬、装甲車、対戦車砲、軍服等、輸出品目を多様化し、ザイール、エチオピア、ルワンダ、コンゴ、ミャンマー、イエメン等に
取引線を拡大している。
![]()
■北朝鮮軍需産業の隘路と転換(conversion)問題
北朝鮮の軍需工業は、規模面においては膨大な水準だが、先端の武器開発技術は、大部分、ソ連と中国の支援下に行われたことから、1990年代以降、重要技術や武器生産、維持に必要な部品導入に小さくない隘路に直面しているものと見られる。即ち、既存の軍需工場が
かなり前にソ連・東欧圏の協力で建設され、技術的に落後し、設備が老朽化し、全体的に効率性が極めて低調な実情であり、エネルギー及び資材消耗率が高く、正常的な生産に困難が大きいものと判断される。
また、エネルギーや各種資材の生産及び供給不足の状況が蔓延しており、先軍政治による「軍事優先主義」にも拘らず、一部軍需工場での生産上の蹉跌が発生しているものと判断される。また、技術的側面から見れば、軍と民間技術の相互連携性も不足し、民間の技術水準が
低く、活用可能性(spin-on)が非常に低い点も重要な限界と把握される。1990年代後半に入り、需要側面において重要な役割を担当したものと把握される武器輸出が大きく減少したことによって、軍需産業全体の稼働率が下落しており、その外に北朝鮮産業一般の問題として、道路、鉄道輸送上の問題、通信・情報基盤の脆弱等も、軍需産業の阻害要因と指摘されている。
結局、北朝鮮経済の相当部分を占めている軍需産業の比重を考慮すると、北朝鮮経済の健全な回復のため、その効果的な転換(conversion)は、死活的に重要なものと見られる。しかし、現在の北朝鮮の立場では、北朝鮮経済の核心的部分を占める軍事経済の全般的瓦解を
引き起こすかも知れないこのような変化を拒否している。過去、旧ソ連の場合は、冷戦当時の軍事経済基地と工場が米国の支援下に民需工業に転換されたが、北朝鮮の場合には、民需転換による費用は、
直ちに新しい民需工業の創出以上の大規模費用が必要とされるものと判断される。
北朝鮮経済の民需転換のためには、先ず、北朝鮮指導部の転換意思が確保された中で、単位企業所別に経済的効率化を行い、その素地の上に自発的構造・品目調整の次元において、軍需工業比率を縮小する方法が
望ましい。指導部次元の転換意思は、何よりも現在のような高軍備負担が
減らなければならず、必要もないという認識、即ち南北間の戦争の危険除去と軍備統制によってのみ可能である。
![]()
■南北経協への示唆点
北朝鮮の軍需産業は、北朝鮮体制の核心を成している部分である。北朝鮮軍需産業の現在と未来は、直ちに北朝鮮全体の変化方向を予想するものと理解することもでき、この点において、この部分に対する注視と共に、積極的対応が必要である。
北朝鮮の軍需産業が備える体制的意味に照らして、現在、林加工及び制限された貿易程度に留まっている南北経協と関連させて大きな意味を付与するのは難しい。ただ、経協の水準がより拡大・深化され、対北戦略物資輸出入と関連して、経協を担当する企業が
非常に注意しなければならないものと判断される。即ち、対北輸出物資の性格に対する綿密な判断と共に、その最終的使用処に対する事前判断が重要であろう。最近、PCの対北搬出と関連して、政策的な
論壇を醸し出すこともあるが、我々の立場において、国際統制体制であるワッセナー体制にだけ依存することもなく、米国の輸出統制制度にそのまま従うこともない。政府が明確なガイドラインを提示する中、企業も朝鮮半島安保状況での意味を
計算して、対北交易に任じなければならないだろう。
北朝鮮の軍需産業が非常に膨大な規模となっており、北朝鮮軍等、軍関連機構の対外経済活動が活発な中、より積極的な次元において、この部分をいかに活用するのかに対する戦略的判断も必要である。事実、
上で指摘したように、北朝鮮軍需産業の民需化とそれなりの効率性増進のための資本主義市場との交流は、北朝鮮体制の変化という点において、非常に注目されなければならない部分である。勿論、これは、経協企業だけが相手にするには、
非常に困難な部分で、政府との緊密な協調が必要な題目だと言える。
![]()
最終更新日:2004/03/19